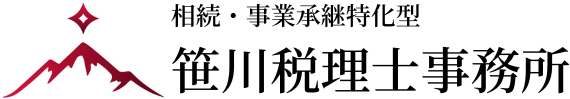DES(デット・エクイティ・スワップ)
DESの種類
◆①現物出資方式と②新株払込方式(疑似DES)がある。
◆①は債権額の時価評価が必要な場合があり、額面と時価の差額が受贈益として法人税課税される可能性がある
②で受贈益課税の可能性はない傾向のため、出来る限り②をお勧めする
【①の場合の処理イメージ】
| 借方 | 貸方 |
| 借入金 1,000 | 資本金等 300 債務免除益 700 |
債権額の時価評価の考え方
国税庁からは文書回答により示されているが、算定方法は明らかにされていない。
但し、債務者となる法人が債務超過の状態や業績が悪化した状態である場合、債権につき回収可能額の算定が必要な場合が多い傾向になると考えられる。
DESコンサルティングの考え方
債務免除益が計上された場合でも、相続税で有利な傾向となる場合がある。法人税等税率が35%、相続税率が55%の場合など。
また、法人税では繰越欠損金と相殺できる場合もあり、シミュレーションが必要。
但し、疑似DESの場合、債務免除益の発生はない傾向となるため、疑似DESを取れるのであればそちらを取ること。
均等割への処置
出資した際、資本金や資本準備金が増加するため、均等割の負担が増加傾向になる旨を説明する必要がある。
尚、均等割の負担増加は増加した資本金、資本準備金をその他資本剰余金などへ無償減資し、その減資額を欠損金の補填に充てた場合は均等割の基準となる額も減少する傾向となる。
これは均等割は以下①、②いのいずれか高い方の金額を基準に算定されるため、減資することで共に金額が減少傾向となるため。
①地方税法上の資本金等の額※1
②資本金と資本準備金の合算額(又は出資金の額)
※1 法人税法上の資本金等の額※2ー無償減資等による欠損補填・損失の補填に充てた額(マイナスの利益剰余金に充当する)※3+無償増資を行った金額
※2 別表五(一)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の額。資本金、資本準備金、その他資本剰余金など株主から拠出された金額(法法2十六)
尚、※3についてマイナス利益剰余金に充当しているか否かを確認するため、各自治体において
・別表五(一) →毎期最新分を添付
・欠損金補填の議事録 →毎期当時の議事録を添付
の提出を申告時に求められる。
※自治体では初年度のみBS純資産の部で利益剰余金の補填を確認する
仮にその後の累積利益により利益剰余金がプラスに転じたとしても、均等割の判定は利益剰余金への充当当時の事実により判定するため、その後の累積利益により均等割が変更される等のことは無いとされている
尚、無償減資等をマイナスの利益剰余金に充当した場合、マイナスの利益剰余金はいつ時点のものかとされているが、「損失の補填に充てた日」とされている(地方税法施行規則第1条の9の6④)。それでは「損失の補填に充てた日」の利益剰余金は、その日までの経理処理により生じた損益を反映させるのかというとそうでは無いと考えられる。これは利益剰余金は期末に生じた当期純利益が利益剰余金へ振り替えられるのであって、期中では原則、当該振り替え処理が行われることは無いためである。結果、マイナスの利益剰余金は減資実施事業年度の前期末の確定した決算書を参照すると考えられる(前記地方税法施行規則は、損失の補填に充てた日における「会社計算規則第二十九条」に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。と定めている。会社計算規則第二十九条は「その他利益剰余金の額」を定めた規定であり、その①二、②三に「当期純利益(損失)金額が生じた場合」、「当該当期純利益(損失)金額」分「その他利益剰余金の額」を加減算することを規定している。当該、「その他利益剰余金の額」の加減算は「当期純利益(損失)」が生じた場合とされていることから、「当期純利益(損失)」の発生は通常期末と考えられることからも、期中「損失の補填に充てた日」の「その他利益剰余金の額」は前期末決算における「その他利益剰余金の額」を参照する根拠と考えられる)
但し、期末の減資はこの限りではない点に留意が必要(期末は当期純利益(損失)へその他利益剰余金の額へ振り替える処理がされると考えられるため)